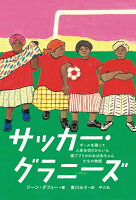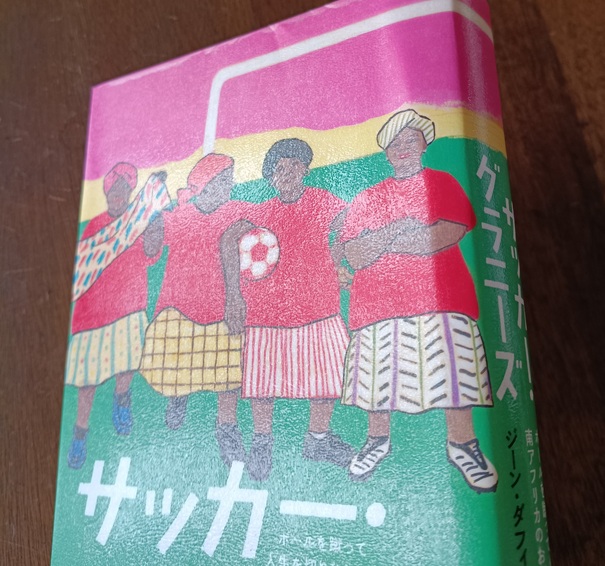
南アフリカのおばあちゃんたちが、サッカーを始めて、人生を好転させていく話。ですって。
無理やり興味を引くような、釣りの言葉は何も使ってない。本の内容を素直に表してあるだけなのに、もうこの一行だけで、読んでみたくなる。思わず手に取って、読んでみました。
どういう本か
冒頭の要約がすべてですが…。南アフリカ共和国の、田舎の黒人おばあちゃんたちが、強力なリーダーを筆頭にサッカーチームを作り、活動する話です。日本に暮らす僕らでも、おばあちゃん×サッカー という組み合わせで、「へえ、元気でいいですね!!」というぐらいの意外性は感じ取ることができますが・・・それじゃまだまだ。それは僕らが、南アフリカのことをほとんど知らないから。
この本を読むと、南アフリカの、田舎の、黒人の、おばあちゃんがサッカーをやるってことが、どれほど型破りなことなのかがよくわかります。
アパルトヘイトは、聞いたことありますよね。南アフリカの悪名高き人種隔離政策。私にとっては、もはや過去の歴史という感覚でいましたが、ぜんぜんそうじゃなかった。いや、当時と比べると劇的に改善はしているでしょう。けれど、その時代を若者として過ごしてきたおばあちゃんたちには、リアルタイムなわけです。そのころ教育を受けることが許されなかった世代が、高齢者になっていきなり生活環境がよくなるわけがない。今でも、アパルトヘイトの影響は残っているし、若者が都市へ出稼ぎに行って、高齢者が孫やひ孫の面倒を見なきゃならない現状はある。
高齢者は、特に高齢女性は、家事をし、孫の面倒を見て、生活費も稼がなきゃいけない。自分のための時間なんてどこにもない。健康を害され、精神的にも疲弊していく。耐えるしかない。精神的に病んだら、魔女扱いされる。
過酷な世界です。ところがそこに、週に何回かサッカークラブで汗を流す、という習慣が入ってきたら、精神的にも肉体的にもとても健康になった。ということなんですね。それだけにとどまらず、クラブ活動がアメリカ女性(筆者)の草サッカーチームの目に留まり、アメリカの大会に招待されて・・・と展開していきます。
血が通った物語として歴史を理解する
そりゃもちろん、アパルトヘイトのことは知っていました。といっても、学校の教科書で知ってる程度の話。それ以上、自分で調べてみようとは思いもしなかった。
でも今回、この本を読んだことで、今までよりずっと理解することができました。サッカーチームの話だけじゃなくて、各章末に、チームメンバーひとりひとりのインタビューが載ってるんです。これまでどんな人生を歩んできたか。
これが生々しくて、刺さる。
そうか、そんなにひどい状況だったのか。人種差別、女性差別、加えて、高齢者が家を守らねばならない現状。
教科書で読んでもピンと来なかった話が、とてもダイレクトに伝わってきます。
ひどい現状の話だけを取り上げた本だったら、こうはならないでしょうね。おばあちゃんサッカーチームが活躍していく話が軸になっていて、それが面白いからこそ、メンバーひとりひとりの話にも興味がわくというか。
高校生の頃は、社会 とくに歴史が大っ嫌いだった私ですが、最近、「人」を軸にした歴史は面白いなあと感じています。ひとりの人の人生を取り上げたYoutubeとか、よく見ます。歴史全体を解説したようなのはあまり見ないんだけど。
なんか、それに近いものを本書に感じるのです。「歴史」ってまとめてしまうと、他人事なのですが、その歴史を経てきた人の人生を聞くというのは、過去の出来事を肌感を持って理解するのに、いいかもしれない。
まあ、そんな難しいことは後で考えるとして、なかなか面白いのでお勧めです。いつもとはちょっと違った本を読みたい方に。面白いけど、面白いだけじゃない本、ぜひどうぞ。