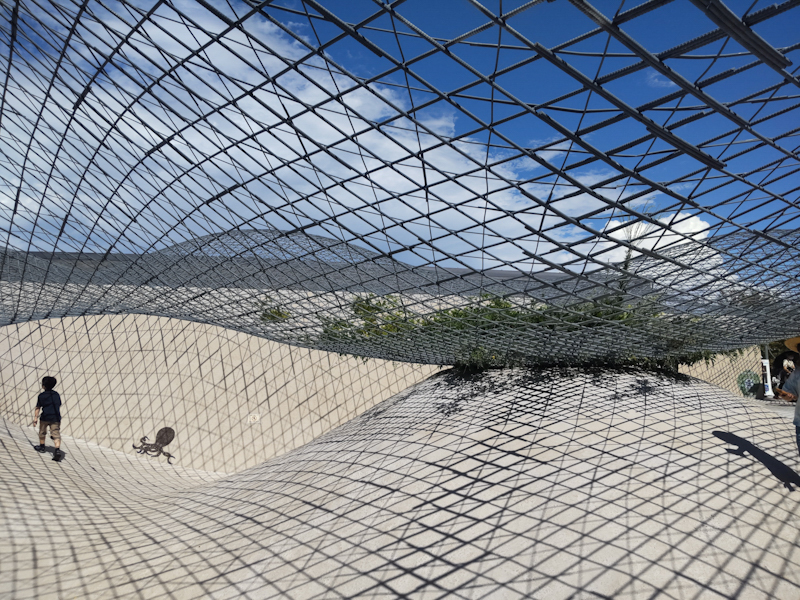
なかなか、すごい本に巡り合ってしまいました。あの安宅さんの本です。
どういう本か
安宅さんご自身でもブログで発表されてるし、たくさん書評はあるだろうから、簡単に。
一言で言えば、「これからの世界をどう作っていくか」という話。「どう作り変えるか」が正しいかな。今の仕組みでは持たないので、全世界、ゼロから考えなおさねば、ちょっとまずいんじゃない?という話です。
そう言うからにはもちろん、ただの批判じゃなくて、これだけ広い範囲でこれだけ具体的に、現実的に考えました、という本。
世界を全部立て直す とは言っても、全世界 画一的な建て直しは解じゃない。地方の過疎化は仕方ないよね、なんて言ってたら、いずれ世界中どこへ行ってもコンクリートジャングルか、本当のジャングルか。それじゃつまんないでしょ。ならば各地方の特性を最大限に活かしながら、「暮らしたくなる地方」を考えよう。もちろん問題はたくさんあるから、細かいところを皆で詰めながら行動していきませんか。という本です。
こりゃすごい。
というわけで、まだ半分読んだだけですが、余りに長く濃いので、いったん書評で振り返ることにしました。書いておかないと忘れそう。
なぜ建て直しが必要なのか
まずこの本前半で得られる、一番大事なこと。言い換えれば「風の谷を提案せねばならない理由」です。
『いまの社会は都市をベースにした構造でできている』(特に運営コストの構造という意味で)
これに気づけるのが大きい。読み始めの頃は、「美しい風景を残さねば」が最大の動機だと理解していました。実際、そこの衝動は大きいけれど、みんなに響くかと言うと微妙。都市も田舎も住んだ上で、やっぱり田舎は良いなぁという年齢層には響くだろうけど、若者に響くには無理があるのでは。と感じてしまいます。
ところが、自治体の費用構造からの話になると、説得力が格段に上がる。田舎はどうやっても暮らすだけで赤字。上下水道維持も、道路も橋も。それを都市からの補てんでどうにか回している。それが全国なんです。夕張だけじゃなくて、田舎の全自治体、最も上手く行ってるところですら、補てんなしには回らない。
これを聞くと、さすがに何とかせねばと分かる。人口が減っていくいま、この構造では先がないぞ。
このままいくと、エネルギー資源とか、CO2をどうこうは解決できるかもしれないけど、みんな都市に肩寄せ合って生きていくしかない。都市部以外、田舎はどんどん人がいなくなっていく。これだけだとあんまり深刻な問題に聞こえないかも分かりませんが、想像してみて下さい。日本から田舎がなくなったら。
岐阜の栗菓子、静岡の桜えび、佐賀のイカ、北海道のカニ・・・そういうものを採って送ってくれる人がいなくなるってことです。全部じゃないけど、少なくともいくつかの特産品はなくなるよね。ちょっと極端な例ですが、都市への人口集中がずっと続くとそうならざるを得ない。(ここは私が想像を進めただけで、本にこう書いてあるわけではないです)
全てが"幸せに"上手くいく方法を考える
で、今までの地方創生とかは、費用構造はそのままで、なんとか地方人口を増やそうとか、都市集中に歯止めをかけようとかの考え方だったわけです。今までの社会の延長線として。まあ普通そう考えますよね。
だけど、費用構造に無理があるんだから、ちょっとぐらい若年人口をどうのこうのしたって無理がある。下がるスピードが緩やかになるだけで、上向きにはならんだろう。
そこである日、安宅さんが閃く。美しい風景と豊かな田舎暮らし。今の日本の課題。これらをつなぐ道が見えたのでしょう。社会の構造を変えればいいじゃない。
そこから作り直そうとは、なかなか思いつかないですよね。ただ一度問題設定してみると、出来なくはない気がしてくる。もちろん相当困難ではある。皆が、数百年レベルで考えて作り直さなきゃならない。全てを。そうすれば、「今のままを持続する」じゃなくて、「より幸せに」暮らせる世界ができるのでは? 本当のサスティナブルってのは、各地方がそれぞれに盛り上がって行かねば持続しないだろう。資源とかだけじゃなく、”幸せ”も持続、というか向上してかなきゃ続かないでしょ。ということなんです。
やると決まればあとは、衣食住とか、国全体で解決すること、各地方で解決することなど分類して、コツコツやっていくだけです。費用構造の話もだけど、各地方が盛り上がる方法についても。大きな方向だけ間違わないように、合わせた上でね。そこをこの本で合わせていこうというわけです。
大きな話すぎるので、半分どころかごくごく一部についてしか書けなかった。こんなレビューじゃ何も分からないかも知れない。ただ、社会をまるっと作り直すという考え方に興味を持ってもらえたら、あとはこの本が詳しく教えてくれます。ぜひこのプロジェクト、進んで欲しいなあ。そしてどこかで手伝いたいなあ。
おすすめ。
住みたい世界があると理解が進む
と、ここで前半レビュー終わるつもりだったのですが、偶然、理想像に近いものをテレビで見てしまったので、付け加えておきます。
それは、京都 法然院の森。
様々な樹木が生え、程よく光が差し込み、美しい苔が保たれ、ムササビが巣作りにやってくる。手つかずではないのに、多様で美しい森があります。おそらくこれが、風の谷が目指す姿のひとつ。確かにこういうところなら住みたいな。森の維持にも協力したいな、と自然と思えるような場所。NHK「ダーウィンが来た」のアーカイブで見られると思います。有料かもだけど。
具体的な場所のイメージが湧くと、よりいっそう理解が進むし、個々の問題も解像度が上がる。みなさんの田舎にも、美しい風景がひとつやふたつ、あるのではないでしょうか。ぜひ、将来住みたい場所をイメージしながら読んでみて下さい。(後半レビューはこちら)
