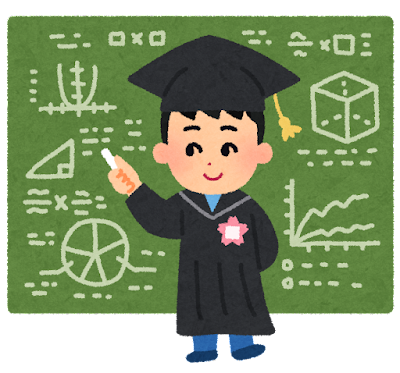
「天才!」という本を読みました。
実は天才とは、生まれつきじゃない。生まれてからどうするか、にかかっているという話。
天才と呼ばれるほどの突き抜けた成果を出す人がいかにして生まれるか。
実は個人の資質よりも、外部要因に恵まれることと、とにかく鍛錬を積むこと。
スタートした時、外部要因によってほんのちょっとのアドバンテージを得た上で、約一万時間という並外れた量の鍛錬を積むことで、そのアドバンテージがとてつもなく大きくなる。
という話。外部要因とは、例えばスポーツ選手になるなら、遅生まれのほうが有利とかそういうことです。
要約だけ見ると、ホントかよと思っちゃいますが、本では見事に筋道を通して論じてあって、納得かつ目から鱗。
この本と、先日の
天は二物を与えうるってこと。 - 永遠に生きるかのように学べ
とを併せて考えると、ちょっと自分でも天才を育てられる気がしてくる。
「生まれつき○○の才能がある人」なんていない。
その子の特性にあった形で環境を整え、チャンスを与え、鍛錬を積ませれば、皆ひとかどの人物になる。
あれ?
「その子の特性にあった形で環境を整え、チャンスを与え、鍛錬を積ませる」
こう書いてみると、全然、新しくない。
聞き飽きた正論。
聞き飽きた正論でありながら、僕は、そして多分皆も、
「やっぱ天才と言われるほどの人は違うな〜」って思いのほうが実感なわけだ。
「自分には無理だ」という思い込みみたいなものかもしれない。
信じたいものだけが見える、と言おうか。
この本を読んで、その思い込みが消えた。
「天才とは99%の汗と1%のひらめきである」というあの有名なセリフが、本当の意味でわかった。
天才でも努力するんだ、なんて意味じゃなく、「そもそも君らとは鍛錬の量がちがうのだよ」という意味だったんだ。
そうすると僕でも、我が子を天才に育てることはできるってことだ。
ちょっとなんか嬉しい。
そう書くと誤解されそうだけど、「天才に育てること」が大事なんじゃない。
「天才に育てることができる」という選択肢がある事が重要なんだ。
「僕の子どもだからまあこんなもんでしょう」じゃないってこと。
鳶が鷹を産むことは珍しくない、ってことなんだ。
そうは言いつつ、鳶が鷹を産むことは易しくはない。
一万時間の鍛錬を積むということは、他の何かに費やす時間を放棄するということを意味する。
それは「やっぱり何かを犠牲にしないとね」なんて訳知り顔の話じゃなく、他の子と違う事に、傍から見てて不安になるほど打ち込み続ける我が子を見守り続けられる覚悟があるか、ってこと。
皆と同じならとりあえず安心、ってのを捨てられるかどうか。
これこそ並大抵の事じゃないよな〜。
天才になるならない、という選択を子ども本人に提供しつつ、選んだ道は覚悟を持ってバックアップする。
すごいプレッシャーだけど、逃げないようにいこう。
【注】
冒頭の本の原題は「Outliers」。突き抜けた人、みたいな意味だと思います。
日本語で天才って言っちゃうとちょっと違うと思うのですが、本記事では訳者の意向を踏襲しました。
「皆が思ってる天才って実はアウトライアーのことなんです」
ていう本の主旨にも沿ってると思うので。
